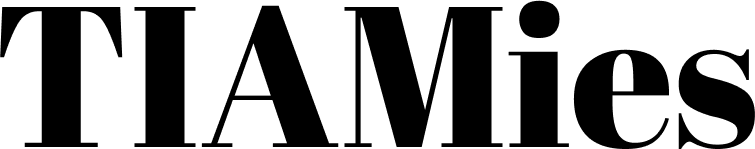終戦、そして広島・長崎への原爆投下から80年。「核絶廃」そして「世界平和」をテーマに掲げたEarth Day Tokyo 2025が、代々木公園で開催された。
オープニングには、被爆者であり埼玉県原爆被害者協議会理事の服部道子氏と、浄土宗和田寺住職で平和活動家の遠藤喨及氏が登壇。世界60カ国の貨幣を用いて製作された「国連平和の鐘」の音が静かに、そして力強く響きわたる中、祈りとともに幕が上がった。
この日、TIAMiesを通して“地球と向き合う姿勢”を届けてくれたのは、4組のアーティスト——Nenashi、MANAKANA、後藤杏奈、MAITAI。それぞれが音を奏で、言葉を紡ぎ、「いま私たちにできる一歩」を確かに伝えてくれた。
今日の平和のために。未来の地球のために。
私たちは、どんな一歩を踏み出せるだろうか。
Earth Day Tokyo 2025(アースデイ東京2025)

日程:4月19日(土)~ 20日(日)
会場:代々木公園(〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町2-1)
Earth Day Tokyo 2025: 公式サイト / Instagram / Facebook
Nenashi:世界を旅するNenashiが語る、未来へつながる小さな一歩
シンガー/ラッパー/プロデューサーとして、国境もジャンルも越えて音楽を届けてきたNenashi。「根無し草(Nenashi)」の名のとおり、世界各地を旅し、文化や人々、自然に触れてきた彼がEarth Day Tokyoの場で語ったのは、人と人が思いやり、関わり合いながら重ねていく、平和への小さな一歩。
地球について考えたり、地球を感じる瞬間は?
Nenashi:「Nenashi」っていう名前は、そもそも「根無し草」から来ているんです。
僕自身、海外で育ったりとか、世界の国とか文化に触れに行ったりするのが好きなので、
現地に行って人に会ったりとか、建造物を見たりとかで、自然に触れ合ったりして、世界を感じるっていうことはありますね。
ソーシャルメディアでも、自分がかっこいいと思っているアーティストの投稿を見かけて、遠いけど繋がれたらいいな、繋がってるなと思う瞬間もあります。
Nenashiさんにとって地球とはどういう概念、存在ですか?
Nenashi:地球を、内側からも外側からも見てみたい。宇宙からも見てみたいなと思うし、地球のセンターってどうなってんだろう、というようなサイエンスフィクション的な興味ももちろんあります。いろんな人と、いろんな国で接してきているので、そんな意味でも常に興味があるものですね。

楽曲や人生観に影響を与えた景色は?
Nenashi:自分が育ってきた環境ですね。緑があるところでも育ってきました。例えば、海があって、山があっての色のコントラストやグラデーションみたいなのって、なんかうまく言葉にできないんだけど、言葉にしたい。そういうものが、自分の歌詞だったり、音にも影響を与えてると思います。
Earth Dayの会場に到着されてから、目に止まったものや「気づき」は?
Nenashi:手書きで作っているものが多く見受けられますね。グループになって、「気候に対してもっと意識変えていこうよ!」みたいなっていうのを、直筆で作ったり、自分で描いた絵もつけたりしている。デザインされてるものもカッコいいと思いますけど、手書きでやってるのもすごくハートがあるし、熱いなと感じました。
未来の地球に残したいもの、残したくないものはなんでしょうか?
Nenashi:良い環境を次の世代に残していきたいですね。もともとテレビ番組『セサミストリート』にも出ていたんですが、環境とか人種問題の観点でも、次の世代のために良い世の中にしていこうっていう想いがありました。変わらずそこは持ってるし、子どもにも与えていきたいなっていう気持ちは常にあります。
残したくないものは、戦争はもちろんですが、ゴミ問題。日本はどちらかというと「綺麗な国」だと思いますが、ポイ捨てするのが当たり前の価値観で生きてる街とか人たちも多いなと思います。「地球温暖化はない」という国のリーダーとかもいるわけですから、考えを変えてほしいとも思いますし、そういう人を選んじゃう国もどうなのかなと。
Nenashi さんが思う「地球の平和のためにできる小さな一歩」は?
Nenashi:今日も電車で思ったんですが、スマホにすごく集中していて周りが見えなくなることがありますよね。例えばそれで「あ、やべえ電車乗り遅れそうだ。」みたいになっても、他の乗ろうとしてる人たちは意外と待ったりするじゃないですか。
そういうちょっとしたことで電車が遅れたりもするし、ちょっとぶつかったりもする。
自分がやりたいなって思うことに集中できるってことはいいことだと思う反面、周りが見えなくなってる人も多いように感じます。ふっと周り見渡すっていうようなことができる人が増えるといいなと思いますし、そういう「気づき」が重要だったりするのかなと思います。
自分の好きなこと、生き方を大切にしながら、地球を大切にするためのヒントがあれば教えて下さい。
Nenashi:やればやるほどできちゃう人もいますが、やってもやってもできないっていう瞬間も絶対あると思います。やろうとしてできないときには、誰かにサポートしてもらうっていうのって非常に大事なんじゃないかなと。
自分自身がサポートしてもらうのも大切だし、逆に、近くの人、家族、友達とかでもいいんですけど、「何かか困ってることある?」みたいなに聞くことが、広い視点で見ると地球につながっていくと思いますね。

| Nenashi
シンガー/ラッパー/プロデューサー。 歌、ラップ、ビートボックスまでを自由に使いこなすソウルシンガー、プロデューサー、Hiro-a-keyによるプロジェクト。 アジア人としてR&B 、ソウルミュージックを世界に向けて発信することに対するレッテルや先入観をなくし、純粋に音楽だけを聴いてほしいという思いから、共通言語である英語で歌い、国籍や顔などアイデンティティーを一切公表せずに活動を開始。 これまでアメリカ、カナダ、ブラジル、バハマ、アルゼンチン、韓国、香港、タイ、カザフスタン、フランス、イギリス、ドイツ、スイスなど20ヶ国以上の地域を転々と旅しては異文化に触れてきたHiro-a-keyは、自らを“根無し草“と重ね合わせ、アーティスト名をNenashiと名付ける。 |
MANAKANA:小さな気づきが、地球へのやさしさを育てていく
“魂の出発”、”魂に響く音霊”をテーマに、ライブ活動やモデルなど幅広く活躍する双子の音楽ユニットMANAKANA。小さな感覚、小さな選択から、やさしさの輪は広がっていく。
Earth Dayで語られた、彼女たちの“気づき”と“願い”の言葉たち。
楽曲を作るにあたって、影響を受けているものは?
MANA:新しいアルバム『十二〜toni〜』をリリースしたんですが、すべて干支の動物をテーマに、初めて曲を書いています。
KANA:「自然があるから生かされている」という感謝の想いを音で表現したい、という気持ちで作りました。
MANA:人間はみんな「身体」と「気持ち」「魂」があると思っています。「魂」にほんとに響く音楽をつくるきっかけになったのは、地球環境の問題や、「地球にどうやったら優しく過ごせるか」を考える機会を与えてくれた、Earth Dayのようなイベントなんです。

地球について考えたり、地球を感じる瞬間は?
KANA:四六時中考えているわけではないですが、生活環境も変わってから自然がずっと隣にあるからか、「今日もきれい、ありがとう」って、ずっと思っていますね。ふとした時に感じることが多いです。
楽曲を作る際に行かれる場所や、影響を受けている場所は?
KANA:いろんなところから受けたインスピレーションをアウトプットに繋げたいので、いろんなものを見る、聞く、場所に行く、を意識しています。
MANAKANA:特定の場所を挙げるとしたら、森、川、林、神社とかですね。
未来の地球に残したいもの、残したくないものはなんでしょうか?
MANA:自然はずっと残ってほしいなと思います。
KANA:残したくないのはゴミ問題。いろんなことへの執着や、「これが当たり前」という考え。当たり前のものって当たり前じゃないことの方が多いと思うんです。
背景を知ることで新しい気づきが得られることもあるから、そうやって「考えるということ」を未来はなっていったらいいなと思うし、自分自身もそうあれるように生きたいなと思っています。
自分の好きなこと、生き方を大切にしながら、地球を大切にするためのヒントがあれば教えて下さい。
MANA:私は「第三者目線」を大切にしているのかもしれないです。毎日鏡を見て「私が映ってる。」と同時に、「その人がいる」みたいな感覚を常に持っておくようにしています。
自分自身と向き合うときにでも、「傍から見ている自分」を意識しないと考えられなかったり、自分は周りからはどう思われているんだろう、これって迷惑だろうかっていうのを考えて、人に優しく、地球に優しくなれたり。
未来の地球のために一緒にできる小さな1歩としてやってみたいこと、まわりにもやってもらえたら嬉しいなということは?
KANA:まずこのイベントに来ることが第1歩だと思いますね。自分と向き合う、地球と向き合う、みたいに気づけることや、気づくためのヒントがいっぱいあると思います。
MANA:動物に触れると、何か変わってくることがあると思います。牛、豚についての問題を知るきっかけになったのは、やっぱり最初は犬だったかな。でも、動物が好きっていうその気持ちだけで十分っていうか、犬の気持ちを知ったりして、何かに優しくすることだけでも、変化が起きていく気がします。

後藤杏奈:地球も人も。わたしたちは、絡まりあいながらここにいる
音楽とともに育ち、世界を船で旅しながら環境に向き合ってきた後藤杏奈。
洋上でも歌声を届けてきた彼女は、自然と人、今と未来——
それらが複雑に絡まりあいながら続いていくこの世界を、静かに見つめてきた。
Earth Dayで後藤杏奈が語った「複雑なものを複雑なままにしておく」の意味とは。
Earth Day出演を決めた理由は?
後藤杏奈:音楽を通じて気候危機の現状を伝えるClimate Live Japanさんに紹介していただいたんです。Earth Dayにはずっと遊びに来てて、まさか出演する側になるとは思ってもいなかったですね。(パフォーマンスしていた時)いつもより暑い、すごく暑い日で、日差しが差してるのに、屋根もないところに皆さん集まってくださって、本当にありがたかったです。
楽曲の制作や、ご自身の考え方に影響を与えている場所は?
後藤杏奈:家の近くに、ちっちゃい時からよく行っている緑地があります。2-3年前まで虫がすごかったんです。飛んでくる虫じゃなくて、芋虫がいっぱいいたりする。
当時は虫が降ってくるのは嫌だったけれども、自分にとって都合のいいものも悪いものも全部ひっくるめて「環境」であり「自然」だから、それを感じたくてよく行っていたんだと思います。嫌だったけど、なぜかそこを必ず通ってたんですよ。
全国的に問題になっているナラ枯れの影響もあって、木々がちょっと前にすごく伐採されてしまったんです。今は歩きやすくなったけれど、虫たちが恋しいですし、木が切られたあともすごく泣きました。

環境問題に目を向けるようになったきっかけはなんでしょうか?
後藤杏奈:近所にどのくらい野生動物がいるかなと、家族でよく観察していました。そのためか、小さい時から「自然にお邪魔しにいく」という感覚を持っていました。
NGOピースボートが主催する「地球一周の船旅」にも3回乗らせていただきました。通訳ボランティアとしてもスタッフとしても乗船しています。船内でも寄港地でもたくさんの出会いがあり色んな思想に触れる中で、植民地主義とは何なのかをすごく考えました。日本ももちろん、植民地支配を進めてしまった国の一つですよね。人の支配と自然の支配が深くつながっていることを知って、もっと環境問題に目が向くようになったかなと思います。
自然を人間の外へ外へと置いてしまう考え方や、人間中心主義的な開発が未だに受け入れられてしまう社会を、心底変えたいという思いがずっとあります。あらゆるいきものとの無数の関わり合いに支えられて今の自分がある、ということを噛みしめていたいです。
好きなことを続けながら、地球のことや自分以外のことを考えるために、何かヒントがあれば教えてください。
後藤杏奈:未来の地球で生きることは、私にとってものすごくミステリアスなもので、わからないことだらけだと思っています。無責任に聞こえるかもしれないけど、私にとっては今しかないっていう感覚も強いかもしれない。ロジックで整理できないことだらけなんですよね。
もし意識的にやっていることを挙げるとするなら、「分けて考えない」ようにしているかも。「人間と自然」も、切り離したところから、ストーリーが失われてしまう。
複雑なものを複雑なままにしておく、簡単に理解しないようにする。粘り強くあらゆるものとともに生きようとする姿勢を大事にしたいと思っています。
自分のことになれば「あれは、嫌だ」とか、「どっちだ」と思うことがいっぱいあるけれど、世界は二元論じゃ到底語れないと思いますね。

| 後藤杏奈
Instagram/YouTube/公式サイト/Spotify/Apple Music 東京都八王子市生まれ。音楽家を夢見た父のもとで育つ。内閣府主催「世界青年の船」やNGOピースボート主催「地球一周クルーズ」に乗船。世界中の若者たちと船上生活を共にした経験が音楽とつながり直すきっかけとなり、2023年にHappiness RecordsよりCDデビュー。 \直近のライブ情報/ 6/7(土)19:00に国分寺のカフェスローで「海にたゆたう暗闇カフェ〜うたとかたりのキャンドルナイト〜」を開催予定。海をテーマにした音楽ライブと参加型の対話の時間にぜひお越しください! |
MAITAI:対話を大事に、違いに感謝し、平和の波紋を広げていく
長野と神奈川、異なる土地に生まれた二人が出会い、自然の中に身を置きながら、息をするように音楽を届けてきたMAITAI。対話を重ね、違いを楽しみ、小さな喜びに感謝しながら音を紡ぐ彼らが、Earth Dayのステージで改めて見つめた「地球と人」、そして「人と人」とのひびきあい。
おふたりが地球や自然環境について考えるようになったきっかけは?
Maria:私は長野県の飯田市という田舎で生まれ育ったんです。「リニアが通る町」といわれていて、小学生ぐらいの頃から「リニアが通ります。あなたはどう思いますか」という時間が多くありました。
子供たちの意見だけじゃなくて、大人が思うリニアの話を聞く機会もあって、「アルプスの中に強い電磁波を持った電車が通ると、さあ、自然はどうなるのか」って考える時間が学生の時からありましたね。
自分の地元の山がなくなってしまうっていう恐れもあって、地球のことについて考えるきっかけになる印象的な出来事のひとつだったのかなと思います。
でも本能的なのか、理由もなく、自然のところにいると落ち着くし、お月様を見ると安心するし、満ち欠けを見て共感したりすることもあって。自然、地球っていうのは、ずっと好きです。
DAI:出身はどちらかと言えば街だけど、田舎に恋焦がれてたというか、ずっと自然が大好きでした。ちっちゃい頃とかは、もちろん車も運転できないし「自然がたくさんあるとこ行きたいな」みたいなのは思ってましたね。
大人になってから植木屋さんでアルバイトを始めたんです。虫を観察する時間があったり、ちっちゃい木の根元に生えてる「雑草」って呼ばれる草にも名前がちゃんとあったり、よく見ると「めっちゃ可愛くね!」って思ったり。草抜きで穴を掘って幼虫くんが眠ってたりすると「めっちゃ愛おしいじゃん!大切にしよう」みたいなのが、やっぱもう不可避で自分の中に入ってきました。
車で旅をするようになってから、大自然と言われるような場所や、水がとっても綺麗な場所に行った時に、「これだ。ずっと待ってた。自然の中で呼吸したかったな」って感じたりとか、落ち葉のところにバッと寝転んで何も考えず過ごすとか時間を求めていたなって気づいて。
そういう体験が徐々に積み重なって、「地球は美しい。守りたいな、愛おしいな」とも思うようになったし、「そんな中で生きてる人間もすごく美しいな」って感じるようになりました。

ステージ側から見えていた景色や、ステージに立っていたときに感じていたことは?
Maria:もちろん2人でMAITAIだし、2人だけで届けたい曲もあるけど、Earth Dayに出演が決まった時、2人だけで代々木公園のステージに立つのは違うと思ったんです。
こんな大切な日には、自分たちの大切な仲間たちと一緒にステージに立ちたいと思ったし、みんなのエネルギーを放ちたいと思った。もっと大きな、いろんな色のエネルギーを届けたいと思ったからだと思います。
それで今回は、愉快な幸せバンド編成でやらせてもらって。考えるというよりは、もう信じていました。自分たちがここで音楽をやることで、「きっと幸せの波紋が広がる」ってことを信じて歌っていましたね。
DAI:いろいろな先人の方々や、自然も、物も、愛とかいろんな想いとかが、自分たちにありがたく集まってきてくれて、僕たちの身体を通して、みんなに広がっていった感覚がすごくありました。それをみんなで気持ちよくシェアして楽しんでいたなっていう記憶があります。
ジョン・レノンのImagineをカバーで1曲歌った時は、個人的にはもう、「ジョン・レノンの魂と繋がっていたな」って。
Maria:こんないい天気の日で、新緑の季節にお外で歌えて、みんなの顔を見ながら演奏できたのは超幸せです。
Earth Dayを通して気づいたことを一つ挙げるとしたら?
DAI:一つ挙げるとしたら、続けていくこと。今まで生きてきたこと、大切にしてきた自分たちの世界とか価値観を、これからも続けていきたいと思っています。
「大きな変化」は自分たちでは作れないかもしれないけど、これからもゆっくり、自分たちの心地よい呼吸で、心地よい楽しさで、自分たちの大好きなことを「ありがとう」って、感謝しながら幸せにやって行ったら、自分たちのまわりからでも世界に平和が広がっていくなと。
Maria:「違うって、めっちゃおもろい」ってことに気づきました。ユースブースでのトークセッション『JK×高校の先生×アーティストが語る 2050年の暮らし』のときにも、使ってる言葉や今持ってる関心の矢印は全然違うのに、軸の部分が一緒っていう共通認識を多分持っていて。
「これって全然違うね。これは一緒だね。今この時間で言葉にできなかったけど楽しかったね。」みたいな、きれいな正解じゃなくて、「違うけど / 同じだけど、おもろい」の感覚を再認識できました。
Earth Dayは「核兵器」を消滅させたい、世界の環境問題について考えるためのテーマを今年は掲げているけれども、それについてずっと考え続けているというよりかは、「もっといい地球にしたい」と思っている人たちが集まっているからかなと思います。
未来の地球に残したいものと残したくないものを教えてください。
Maria:未来の地球に残したいものは、愛。残っていくと信じているし、無くならないものだと信じてる。未来の地球には愛がある。
DAI:残したくないものは、武器。武器は必要ない。戦うことよりももっと、会話することの重要性がどんどん増していってほしいなと思うし、そう信じて普段も生きています。
好きなことを続けながら、地球のことや自分以外のことを考えるために、何かヒントがあれば教えてください。
DAI:俺らももう8年くらいここで生きてるから麻痺しちゃったこともあるかもしれないけれど、カップラーメンの中にも豚さんのお肉とか乾燥ネギとかが入っていて。もともとは「自然の恵み」だったものだけれど、そういう命が見えなくなってるから、感謝ができてないなと思っていました。
例えば、鮭のおにぎりを食べるときに、「誰か作ってくれたお米、ありがとう」とか、「工場で働いてくれてる人が、いろんな思いをして作ってくれてんだな」とか、ちょっと思いを馳せると、よりありがたく、より美味しく感じるし、頂いてる命だけじゃなくて、作ったものに関わった全ての命にも感謝を感じます。
目に見える、大きな命、人間の命、クジラの命にフォーカスしがちだけど、命の価値に本来違いはないからさ。
MAITAIのおふたりが思う「地球の平和のためにできる小さな一歩」は?
DAI:「喧嘩」ではなくとも違和感とか、モヤモヤしてるけどお互い話さない時には、自分から謝ったり、自分から質問をして理解し合うための姿勢をとること。
自分としても心穏やかになるし、あっちもほんとは話したかったけど、お互いのエゴとかプライドで戦っちゃってる時があると思います。ほんとはみんな分かり合いたいし、ほんとはみんな仲よくやりたいから。
Maria:地球の平和のためにできる小さな1歩は、「違いをおもしろがること」だと思います。
「違うこと」って悪いことじゃない。みんな違うのが当たり前で、違うからこそ共鳴したらめっちゃおもしろいし、相手の違うっていうのを知れた時に、自分はこうだなって思えるから。